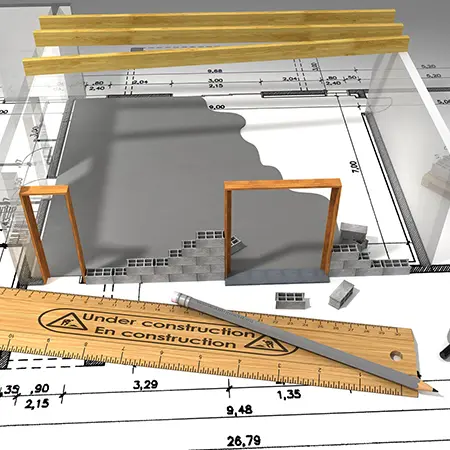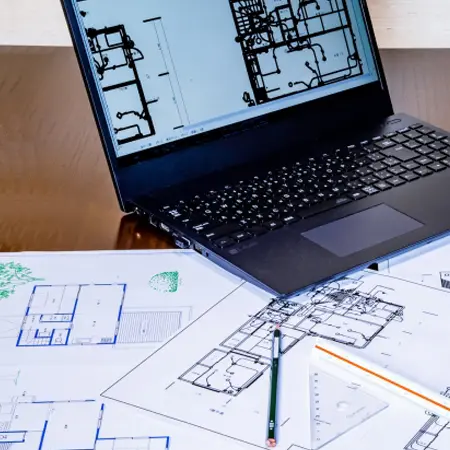2025年の建築基準法の改正では、既存の耐震基準が直接変更されるわけではありませんが、耐震性能の確認が厳格化されます。これは主に住宅の省エネ化に伴う建物の重量増加と、これまで構造審査が省略されていた 4号建築物の特例が縮小されるためです。
ここでは、2025年の法改正のポイントを分かりやすく解説し、これから家を建てる方が知っておくべき注意点と後悔しないためのヒントを紹介しています。
※このページの記事や画像には、一部AIが自律的に生成した箇所が含まれております。
- 2025年法改正の目的と主な内容
1-1.4号特例の縮小
1-2.構造審査の厳格化
1-3.省エネ基準の義務化 - 2025年以降の家づくり、具体的にどう変わる?
2-1.建築コストへの影響
2-2.設計の自由度への影響
2-3.工期や建築スケジュールの影響 - 後悔しない家づくりのために、今からできること
3-1.情報収集
3-2.パートナー(建築会社)選びのポイント
3-3.長期的な視点での検討 - まとめ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

2025年の建築基準法改正は、直接的に既存の耐震基準を変更するものではありません。しかし省エネ性能の向上に伴い建物が重くなることや、建築物の安全確認をより厳格に行うこと、国が掲げるカーボンニュートラルという目標に向けて、より高性能な住宅の普及を目的とするために、今回の法改正が行われました。
主に 4号特例の縮小・構造審査の厳格化・省エネ基準の義務化の3つの点が大きく変更されます。
4号特例の縮小

これまでの建築基準法では、4号特例と言われる 4号建築物(小規模な木造住宅)の構造審査が一部省略されておりました。
しかし、2025年からこの4号特例が大幅に縮小されております。具体的には、これまで新築の木造住宅の多くが省略されていた構造審査を対象とし、建物の安全性をより確実に確保するためです。
構造審査の厳格化

4号特例の縮小に伴い、これまで構造計算書の提出が不要だった小規模な木造住宅も、構造計算や壁量計算といった構造審査の書類提出が義務化されます。これにより建築士が建物の安全性をより詳細に確認することになります。
省エネ基準の義務化

2025年4月から、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されております。これにより断熱性能や省エネ設備の導入が不可欠となり、住宅の性能が全体的に底上げされることとなります。省エネ基準の義務化は地球温暖化対策の一環であり、住まい手の光熱費削減にもつながります。
2025年の法改正は単に法律が変わるだけでなく、実際の家づくりにも大きな影響を及ぼします。建築コスト、設計の自由度、そして工期やスケジュールなど、多岐にわたる変化が予想されます。
2025年建築基準法改正が家づくりに与える影響
| 項目 | 2025年法改正後の変化 | 建築コスト・設計・工期への影響 |
| 建築コスト | 構造計算や詳細な設計図書の作成義務化 省エネ基準適合のための高性能な建材・設備導入 |
【増加】 構造計算費用、設計料、高性能建材・設備費用が全体的に上昇する可能性があります。 |
| 設計の自由度 | 構造計算の厳格化 耐震性や省エネ性を考慮した設計が必須に |
【一部制約】 大きな吹き抜けや複雑な形状など、これまでは比較的自由だった部分に構造的な制約が増える可能性があります。 |
| 工期・スケジュール | 建築確認申請手続きの厳格化・複雑化 | 【延長の可能性】 着工までの申請手続きに時間がかかるため、家づくり全体に余裕を持ったスケジュールを組むことが重要になります。 |
建築コストへの影響

最も直接的な影響は、建築コストの上昇です。これまでの 4号特例が縮小されることで、多くの住宅で構造計算が義務化されます。これにより構造計算費用や、より詳細な設計図書の作成にかかる設計料が増加する可能性があります。
また、すべての新築住宅に義務化される省エネ基準に適合させるため、高性能な断熱材やサッシ、設備機器の導入が不可欠となり、建材費用も上昇すると思われます。
設計の自由度への影響

構造計算の厳格化は、設計の自由度に影響を与える可能性があります。
大きな吹き抜けや開放的な空間、複雑な形状の建物など、これまでは比較的自由に設計できていた部分にも、構造的な制約が加わることになります。これは耐震性をより厳密に確保するためであり、設計段階から専門家との綿密な打ち合わせがこれまで以上に重要になってきます。
工期や建築スケジュールの影響
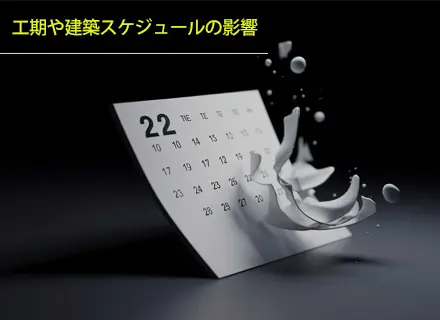
構造計算の義務化や審査の厳格化により、建築確認の申請手続きにこれまで以上の時間がかかることが予想されます。
今後は着工までの期間が長くなるため、家づくり全体に余裕を持ったスケジュールを組むことが重要になります。特に住宅ローンや仮住まいなど、資金計画や生活設計に影響が出る可能性があるため、早めの情報収集と計画が不可欠です。
法改正による変化は、一見すると手間やコストが増えるように感じられるかもしれません。しかし、これらはより安全で快適な家を手に入れるための前向きな変化です。後悔しない家づくりを実現するために、今からできることを3つのポイントにまとめました。
情報収集
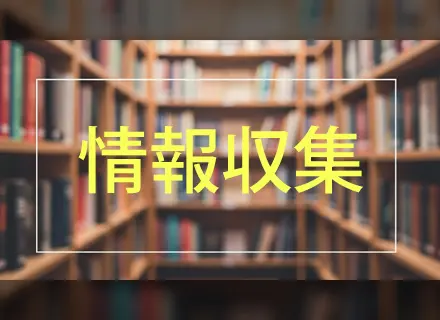
インターネットやSNSには様々な情報があふれておりますが、誤った情報も混在しております。まずは国土交通省の公式発表や信頼できる専門家、建築士、住宅会社が発信する情報を確認することが重要です。
法改正の内容を正しく理解することができれば、不要な不安は解消できますし、適切な判断を下せるようになります。
パートナー(建築会社)選びのポイント
法改正後の家づくりを成功させるためには、頼れるパートナー選びが最も重要です。以下の点を参考に建築会社を選ぶことをお勧めいたします。
● 法改正への対応状況
2025年以降の新しい基準や手続きに精通している。
● 技術力と実績
厳しい構造審査に対応できるだけの高い設計・施工技術・実績を持っている。
● コミュニケーション
担当者は専門用語だけでなく分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれる。
長期的な視点での検討
法改正は住宅の性能を長期的に向上させるものです。建築コストの増加にばかり目を向けるのではなく、長期的なメリットも考慮に入れておきましょう。
● 省エネ性能の向上
光熱費の削減につながり、家計の負担を軽減します。
● 資産価値の維持
高い耐震性や省エネ性能は将来的に家の資産価値を維持・向上させる要因になります。
● 安心感
大きな災害(地震や異常気象)に備えた安全で安心な暮らしを手に入れることができます。
これらのメリットを総合的に考え、納得のいく家づくりを進めることが大切です。

2025年の建築基準法改正は、これから家づくりを始める方にとって、一見すると負担が増えるように感じられるかもしれません。しかしこの法改正は、安全性・快適性・環境性を向上し、優しい住まいを社会全体で実現するためのものです。
この変化を前向きにとらえ、正確な知識を身につけ、信頼できるプロと共に家づくりを進めることが、快適な暮らしを支える理想の住まいを手に入れることにつながります。